IT業界における客先常駐という働き方は、長年にわたり多くのエンジニアたちにとって一般的なキャリアパスの一つとなっています。
しかし、このような環境で働く中で、エンジニアが自身の技術的なスキルや知識を十分に活用できずに、キャリアの成長が停滞する「飼い殺し」という問題に直面することがあります。
本記事では、ベテランITエンジニアの視点から、客先常駐で働くエンジニアが遭遇するこの問題の詳細と、それに対する実践的な解決策について詳しく掘り下げていきたいと思います。
飼い殺しの実態とは
まず「飼い殺し」とは、文字通りエンジニアが新しい技術やプロジェクトに関わる機会が与えられず、既存の技術や知識の中でのみ仕事をすることを余儀なくされる状態を指します。
この状態にあるエンジニアは、技術の急速な進化が特徴のIT業界において、自己のスキルセットが陳腐化してしまうリスクに直面します。
特に、客先常駐の仕事では、エンジニアがクライアントの目の前で成果を出すことが求められるため、新しい技術を学ぶための時間を見つけることが困難になりがちです。
具体例を通して見る飼い殺しの影響
例として、クラウドコンピューティングや人工知能(AI)といった最新技術に興味があるエンジニアが、レガシーシステムの維持管理を主な業務とする客先に常駐している場合を考えてみましょう。
このエンジニアは、新しい技術を学び、キャリアを通じて成長するチャンスを見出すのが難しくなります。
これは、個人のモチベーション低下に繋がるだけでなく、業界全体のイノベーションの遅れにも影響を及ぼしかねません。
問題発生の背景
この問題は単に個々の企業やプロジェクトの問題ではなく、IT業界の構造的な問題として捉えるべきです。
客先常駐という業務モデル自体が、エンジニアがクライアントの即時の要求に応えることを最優先するため、技術的な成長やキャリア開発が後回しにされがちなのです。
また、エンジニアを派遣する企業の文化やマネジメントスタイルも、この問題を悪化させる一因となっています。
社員が客先に気に入られ常駐を長く続けてくれればくれるほど、毎月企業に一定額の報酬があがります。新規に営業するよりも楽に報酬があがるのです。(社員の給与は上がりづらくなりますね。。。)
うまくいけば、さらに増員も期待できます。
短期的な業績を重視するあまり、エンジニアの長期的なキャリア成長やスキルアップに必要な投資がおろそかにされるのです。
解決策:個人と組織の両輪で
個人レベルでの取り組み
飼い殺しの問題に対処するには、まずエンジニア自身が自らのキャリアとスキルセットの管理者であるという意識を持つことが重要です。
具体的には、仕事の合間を縫って最新技術の学習に励んだり、オンラインコースや勉強会への参加を積極的に行ったりすることが挙げられます。
さらに、自身のスキルを活かせる新しいプロジェクトやポジションを積極的に探求することも重要です。
社内外での人脈を広げ、様々な情報を収集することで、新たな機会を見つけ出すことが可能になります。
他社や他業界などからの情報収集を元に今の自分の価値を改めて見つめ直しましょう。
あなたが思っているよりも世間はあなたを高く評価する可能性も少なくありません!
組織レベルでの施策
一方、企業側もエンジニアの成長を支援する体制を整える必要があります。
これには、客先常駐のエンジニアにもキャリアパスを明確に提示し、定期的なスキルアップのためのトレーニングやセミナーへの参加を奨励することが含まれます。
また、エンジニアが客先常駐の合間に社内プロジェクトに参加できるようにすることで、新しい技術や異なる業界の経験を積む機会を提供することも考えられます。
上記のような施策を行う会社も増えてきましたがまだまだ中小のSES会社では厳しいかもしれません。
(しかし、ただエンジニアを客先に送り込むことだけを考えているような会社はとっとと辞めた方が賢明です。)
まとめ
客先常駐で働くITエンジニアが飼い殺しの状態に陥らないようにするためには、個人の積極的な学習とキャリア構築の努力と、企業による支援体制の構築が不可欠です。
エンジニアとしての自己成長を追求し続けること、そして企業がその成長を支援し、促進することで、最終的には業界全体の発展とイノベーションに貢献することができるでしょう。
この問題に真摯に取り組み、実践的な解決策を実行することが、今後のIT業界における持続可能な成長への鍵となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
またお会いしましょう!
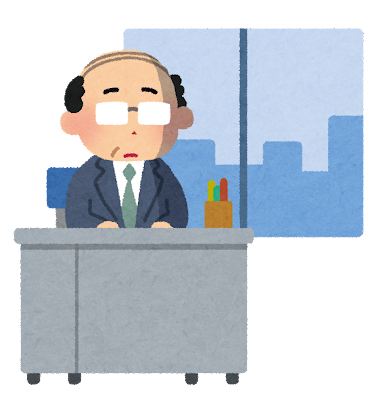
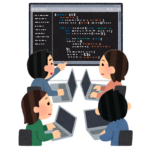

コメント